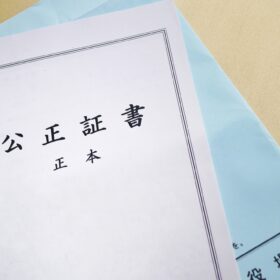相続のご相談を受ける中で、土地の境界に関するトラブルは少なくありません。
特に「赤線」「青線」と呼ばれる境界線は、相続手続きや土地利用に大きな影響を与えます。
本記事では、相続専門行政書士の立場から 赤線・青線の基礎知識と、安心して相続手続きを進めるためのポイント をわかりやすく解説します。
⸻
赤線・青線とは?
赤線とは?
赤線は「里道(りどう)」などの 法定外公共物 を示します。
形式上は「公の土地」として扱われ、払い下げや用途廃止には必ず行政との協議が必要です。
青線とは?
青線は「水路」を示し、境界の基準になる線です。
水利権や用途廃止に関わり、相続後の土地利用に大きな影響を及ぼすことがあります。
この赤線・青線を正しく理解していないと、
相続で土地を分ける際に 思わぬトラブル に発展するケースが多く見られます。
⸻
相続と赤線・青線の関係
実際の相続相談でよくあるケースとして、
「測量を何度繰り返しても境界が確定しない」という事例があります。
原因は、土地の一部に赤線や青線が入り込んでいるためです。
この場合、単に測量するだけでは解決できません。
必要なのは、行政との協議と地域の同意形成 です。
⸻
行政書士の役割
赤線・青線に関する業務は、司法書士や土地家屋調査士とも重なりますが、
「用途廃止」「払い下げ」などの申請は行政書士の業務領域 に含まれています。
行政書士の仕事は、図面を読むだけでなく、
「専門的な制度を依頼者にわかりやすく翻訳すること」。
さらに、
• 市役所の道路課との協議
• 自治会長や近隣住民への説明や調整
を通じて、安心して相続を進められるようサポートします。
⸻
赤線・青線を処理する流れ
行政書士が関わる場合、手続きは以下の流れで整理されます。
1. 道路課へ相談
払い下げ可能かどうかを事前に協議する。
2. 依頼者への説明
行政の言葉を「生活の言葉」に翻訳して伝える。
3. 地域との調整
自治会や近隣住民に説明し、合意形成を図る。
4. 専門家との連携
測量は土地家屋調査士、登記は司法書士と連携して進める。
「用途廃止 → 払い下げ → 登記」までを一気通貫で進めることが可能になります。
⸻
まとめ:安心の相続には「調整力」が必要です。
• 赤線・青線を理解すること
• 自治会や近隣住民の協力を得ること
• 行政と地域、専門家をつなぐこと
これらは、相続の現場で安心をつくるために欠かせません。
行政書士は 制度の翻訳者であり、地域と行政をつなぐコーディネーター。
だからこそ、境界の赤線・青線に関する実務は行政書士が本領を発揮できる分野です。
⸻
相続で境界に不安がある方へ
「土地の境界に赤線や青線があるけれど、どうすればいいの?」
「測量を繰り返しても解決しない」
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
玉野行政書士事務所は、
相続に関する総合的なサポートと、地域・専門家との調整を通じて、
ご依頼者様に安心を届けることを使命としています。
お問い合わせ電話番号
ご相談などお気軽にお問い合わせください。